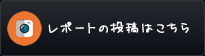担当者より【明石海峡ショア青物タックル】
●441兵庫県日本海側
●444兵庫県日本海側
●454兵庫県播磨灘
マサさんより
お読みの皆さんへ
マサさんのレポートをうけてちょい説明。
兵庫県には瀬戸内側と日本海側、2つの海に面してます。
兵庫県瀬戸内側は、
主に神戸~明石海峡周辺で、ブリ系。
日本海側は但馬海岸とも呼ばれ、ブリ系ヒラマサ系、
それぞれ半々くらいでしょうか。
ブリ系に偏る時もあれば、
ヒラマサばかり当たる日もあります。
近郊瀬戸内側のブリ系、日本海側のヒラマサ。
そこにそれぞれ、シオやサワラが絡んでくる。
両方を楽しむマサさん、いい遊び方ですよね。
No.454のレポートで
「朝マズメをが何もなくすぎて諦め気分」のところで、
ちょっと私の私見話しさせてください。
自分は、自宅近郊の波止場(明石海峡です。
ぶっちゃけ歩いてでも釣り場にイケる距離)で
釣りをするときは、朝はめったに行きません。
朝はここ数年、散歩以外行ったことなくて、
午後がメインです。
理由として、「青物は潮次第」と実感してること。
これが一番大きな理由です。
昼でも、ドピーカンでも、まったく問題なく釣れます
(後述しますが、潮速にもよると思う)
また、朝は混雑してるし、
来てる釣り人もなにやら殺気(?)立ってたりする。
その雰囲気のなかで釣りするのが苦手。
という感じで、
丸一日やれる日なら
朝マズメの方々が帰り支度をはじめる
10時くらいに釣り場に到着して、夕方までやるとか
午後2時~3時くらいの中途半端な時間に行って、
夕方までやるとか、そんな感じが多いんですけど、
結果としては
日中でも、ガッツリ普通に釣れます。
96センチ、10.2キロのメタボブリが釣れたのは、
波止の上に自分含めて4人しか居ない、
夏の真っ昼間でした。
もちろん多少は朝夕マズメが、
ベイトの移動なんかで食いがたつこともあると思いますが、
ある程度潮の走る釣り場では、
そこはあまり関係ないですね。
目安として、80グラム以上が必要な釣り場の場合、
時間マズメは関係ないと感じますよ。
一方、湾奥の釣り場の場合は
流入河川やベイトなどの影響が大きいようで、
朝夕マズメの影響が顕著のようです。
そこが、釣り場の特性によって違うのだと思います。
潮の変化がある釣り場なら、
魚は潮でちゃんと捕食します。
今回の、マサさんの釣果がまさにその好例!
画像の、その釣り場なら、浅いとはいえ潮は走る。
昼間も投げ続けていれば、
潮の圧の変化はわかり、
そのタイミングでバイトをとれますね。
今後も投げ続けて、釣果重ねてください!
海峡周辺。
自分の仲間の最大サイズを付け加えておきます。
14キロ、これはプラグ。
画像を見せてもらいましたが、ほぼ丸のみ。
プラグは口の中に飲み込まれていました。
13キロ、これは先輩が釣ったもので、レベル100グラム、
エッジバーンシルバーだったと思います。
ほかにも、10キロオーバーはけっこうありますよ。
近郊とはいえ、普通に大型が出ます。
大型が来たら、基本的には竿はたてず、走らせます。
ツッコミがおちつけば、はじめて、
寄せるために竿を立てます。
ノットはもちろん、ヒット後のシュミレーション、
ランディング位置の想定、
両隣の人の雰囲気(コレ大事です)。
お書きのように、
「サイズアップをめざす」ぜひ、実現してください。
自分が近郊の釣り場で使っているタックルを、
ご参考までに書いておきます。
①竿
▶小潮~中潮干潮前後.通常の風速時
エイムス ブルーアロー110H
ジグ60~100
ややスローですが、ジャーク中のジグの移動が安定します。
ティップ~ベリーにかけての入り込みが、
60~80グラム使用時に絶妙で、水中感知が容易です。
干潮時のテトラ帯から、
ジグを損傷させずにピックアップできるのも
このレングスの良さです。
▶明石海峡、大潮干潮前後、通常の風速時
ヤマガブランクス ブルースナイパー106H
ジグ80~150
80~100のジグが気持ちよく使え、飛距離が出ます。
竿がジグを運んでくれる感覚が掴みやすい。
ナイロンリーダーを使っているような入力で、
フロロカーボンリーダーをリリースできます。
ちなみにこのロッドでは、釣友が昔男女でキハダ20キロ
目の前でランディングしてます。いまだに長持ちしてます。
明石海峡での私の釣りには絶対に必要な竿です。
▶明石海峡、干潮爆風時
ダイワドラッガーブレイクスルー910JS
ジグ125~250(ベリーに乗せて投げれば250使えます)が
幅広く使える絶妙のベリーです。
ジグ操作のための竿ですね。
レングス的に干潮、満潮、波止はもちろん
磯、離島問わず汎用性が高いこと。
また疲労が少ないベンドカーブの推移を持っているため
1日中投げ続けても疲れず操作できる。
唯一無二ですね。
▶明石海峡小潮~中潮 満潮位
UFMウエダ
シューティングボロン100MH
軽く、おそらくブランクが、薄いゆえに
扱いに気を使いますが、
ブランク内で反響するような感覚で感度が良く、
遠投の必要がない満潮前後にはこれ一択です。
魚の絡みを感じやすい。
あえて、ギリでボトムとれるジグウェイトで、
ギリギリの感知を楽しむことができます。
ジグウェイトは50~60がジャスト。
潮が止まり始める、あるいは動き出す。
その一瞬を軽量ジグで狙い撃つため、
使用時間は1日のうち30分ほどですが、
そのときの効果は強烈です。
▶明石海峡大潮 満潮位
1、ドラッガーブレイクスルー910JS
多用するジグウェイト80~130を、ロッドを変えずに、
同じジャーク感覚で使用できる。
多点シングルフットガイドで、
ロッドの強度に対して操作感が極めて軽快で、
感知に優れる。
風が強くなれば150までは安定的に、
爆風なら250も投げれる。
これ一本が、
投げ続け、ジャークし続けるための疲労感のなさ、、
感度、一体の飛距離、バットのリフティング能力。
私の求めるジグロッドに必要なものが、
高次元に凝縮されています。
グリップはサンドペーパーで、
直径で約2ミリ細くしています。
ブランク特性から、疲れず、1日中投げられる。
2、МCワークス、ワイルドブレイカー104 パワー7.5
これは、明石海峡大潮時、
遠投用に別注で作ってもらったモデル。
人が多くてもはるか向こうの海面まで
100~120グラムのジグを着水させるためのもの。
飛距離重視。
パワーもあり、10~20キロの魚はこれでいくらか
釣っていますからパワーは、十分です。
そのパワーを、
私の場合飛距離を稼ぐのために特化したものです。
100グラムで飛距離を出せる竿が、
実はあまり存在しないので、その適切な長さからくる、
キャストの時のリリースゾーンの広さから、
キャストにも気を使わずに飛距離が楽に出る。
とても重宝しており、離島もこの竿です。
②明石海峡メインライン
PE0.8号~1.5号。
8割方1.2号を使用しています。
新浜漁港でのヒラマサ86センチ、
ブリ96センチ10.2キロは、いずれも1.2号です。
釣行時間トータル40時間ほどで、
スプールに向きを変えて巻き直すため
300メートル巻きを使っています。
③明石海峡ショアジギング、青物に限ってのリーダーシステム。
ナイロン5号~7号約4.5メートルに、
先糸としてフロロカーボン5号~8号を約1.5メートル、
三つ編みで連結。
投擲のときは結束部分を
トップからギリギリで出して投げます。
なぜ、ナイロンがそこまで長いのか?
このシステムのメリットは、
明石海峡湾岸では計り知れないと実感しています。
これだけで、異様な説明時間を要しますので、割愛します。
先糸に関して言えば、フロロなのは、
最後のランディングでのテトラエッジでの
擦れを回避するためです。
なを、5号の場合はフロロの先をビミニツイストなどで、
あらかじめダブルラインとしてから、
リングに結束することで振り切れを防ぐ必要が、ありますが、
6号の場合はそのままノットで
120グラムクラスなら切れません。
これもナイロンの伸びの恩恵なのですが、、。
④リール、あまりこだわってません。
ロッドにセットしてからの巻き心地、
リズム感を気にする程度です。
けっこう適当。
ドラグは3~4キロくらいですので、
市販されてる6000円以上のものなら、
全く問題ないと思います。
自分は98ツインパワーを使うことが多いです。
⑤ジグ、10本選ぶなら、潮名と流速が必ずしもリンクはしません。
とはいえ、目安として小潮ら中潮大潮表現してみます。
・小潮 50 1本
60 2本
80 3本
100 2本
120 1本
150 1本
・中潮 60 1本
80 3本
100 3本
120 2本
150 1本
・大潮 60 1本
80 1本
100 2本
120 3本
150 2本
200 1本
⑥鈎、ほぼ、ファイアフック自作。
ごくまれに早掛
ツインで使用、いろいろ持ってます。
ハリの種類を多く待つと、選択肢が増えすぎて
手返しが悪くなるので、フックはほぽファイアのみ。
ツイン3/0.4/0 4.5/0
を使い分けます。
話しが大きく飛んでしまいましたが、
ときおり質問いただきますので、
マサさんレポートへの返信の場をお借りして、
現時点でのものを書いてました。
マサさん、
おそらくどこかでお会いするでしょう。
宜しくお願いします。
良い釣りを!

●445 鹿児島県南薩沖磯
●494鹿児島県地磯
より
ちゃきさん
No.445では、水面に群れている湧きグレ(※1)を貫通し、
脳天締めまで完了してしまった撃投ノーマルの画像が、
インパクトあります。
かつて、ポラを貫通したエアロを見たことがありますが、
グレは初めてです。
鉄砲の銃弾は空中でこそ、その慣性エネルギーが生かされ、
水面下1メートルでは水の抵抗があるため、
殺傷能力が急激になくなるらしいですね。
湧きグレやボラも、
あと50センチほど沈んで泳いでくれていたら
直撃しても貫通しなかったのでは、、。とは思います。
(注※1 「湧きグレとは、まるでボラの群れのように、
グレが群れ、表層でシャバシャバしている状態」を、
主にフカセ釣り師がそう呼びます。
一般的に湧きグレは釣りづらいようです)。
撃投シリーズでは、内部にステンレスの鋼板が、
それぞれのウェイトに対して
最適化されたフォルムで、内蔵されており、
これが場合によっては対象物に衝撃を与えますから、
投擲方向の安全を確認してからキャストをお願い致します。
ステンレスは、鉛よりも硬度が高いため、
衝突した時の破壊力も大きくなります。
ジグの変形を抑え、着底感度を高めるタフボーン。
変型や損傷が避けられないのがショアの釣り。
着底感度は船と比べると鈍くなるのも、ショアの釣り。
そのふたつに対策したのが、タフボーン。
いまだ撃投だけの個性です。
ロッドプロテクターにタフクラ35にボディプロに、ジグに、
ほとんどの撃投ギアを使っていただいてるちゃきさん。
レイドバックの持ち得る能力を
ガシガシ引き出してくださってますね。
激しく動くことで、アンカー効果を得る
(撃投で言えばエアロのような)ジグは
選択肢が、膨大にあるのですが、
動きを抑えながら、あれほどアンカー効果のあるジグは、
おそらくレイドバックだけではないかと思います。
フォールの水平姿勢も、一味添えて
唯一無二のジグになっていると思います。
レポートNo.494の釣行。
ええ写真です!
瀬泊まりのヨロコビは、
いわゆるキャンプとはまた違うヨロコビ。
翌朝への期待感
非日常での仲間との盛り上がり
磯の怪談のリアルさ(笑)
すべてが極上ですね。
我々の場合、目的がはキャンプではなく釣り活動ですし、
手段としての「野宿」。荷物も最低限のパッキングで。
だからこそ、凝縮される、惹かれるものがあるのでしょう。
そうそう、最近自分が知った、
瀬泊まりでのナイスアイデアを
2つ皆さんにも共有しておきたいので書きます。
①バイクシートを利用する。
瀬泊まりはもちろん、
安価だし、コンパクトだし、なにより迅速に対応できる。
急なスコールでもめっちゃいいらしい。
そんなふうに完璧だそうで、
これは撃投サイトでも紹介させていただきます。
自分もやってみようと思います。
内部にちょっとした半円の支柱的なものを使えば、
ほぼ、山岳ツェルトのような状態にできますね。
奄美の釣友から教えてもらったものですが、
これは素晴らしいアイデアだと思います。
なんせ、我々はキャンプと言うより「野宿」ですので。
もう一つ、磯でもよおしたときの処理方法に、
新聞紙とビニール袋で、安全に用便をすませ、
衛生的にも、環境的にも、エコに処理できることです。
これは、誰からお聞きした覚えてないけど、
これも素晴らしいですよ。
わたしは数年前からこの方法です。
風が強いときは新聞紙が想定外にめくれ上がって、
自分の尻にになったりすることがありますから、
そこはジグ文鎮をを使うなど、なんなりと対応ください。
このふたつ。すごくいいですよ。
瀬泊まりについて書いたところで、
さて、本題です。
ちゃきさんはレイドバック、もう使いこなしてますね。
動きの幅が小さい、動きが少ないことが、
どういう結果に繋がるのかを、じっくり解説してくれてます。
実は以前より、SNSを通じ、
ちゃきさんにはいつか南薩へご一緒させていただくお話しを
しているところでもあります。
まだ、お会いしたことはないんですが、
私は営業担当者として、
毎月鹿児島県へ営業にいくものですから、
今年の秋には実現させてほしいですね。
このレポートのように、
それだけ釣れたらサイコーじゃないですか!
ちゃきさん流の、考察やなにかを、
一緒に聞かせていただきたいです。
そんときは、自転車カバーと新聞紙持参でまいります。
宜しくお願いします。


- 2010~2015年9月までの過去投稿はこちら (1)
- フィールドテスター (72)
- 担当者2より (51)
- 担当者より (545)
- 撃投サイトへのレポートはこちらから (1)
- 撃投モニター (139)
- 撃投釣果投稿 (2,971)

- 2025年12月 (46)
- 2025年11月 (75)
- 2025年10月 (70)
- 2025年9月 (31)
- 2025年8月 (28)
- 2025年7月 (54)
- 2025年6月 (54)
- 2025年5月 (74)
- 2025年4月 (54)
- 2025年3月 (11)
- 2025年2月 (17)
- 2025年1月 (8)
- 2024年12月 (38)
- 2024年11月 (52)
- 2024年10月 (96)
- 2024年9月 (72)
- 2024年8月 (63)
- 2024年7月 (98)
- 2024年6月 (52)
- 2024年5月 (97)
- 2024年4月 (27)
- 2023年12月 (51)
- 2023年11月 (63)
- 2023年10月 (54)
- 2023年9月 (48)
- 2023年8月 (51)
- 2023年7月 (40)
- 2023年6月 (41)
- 2023年5月 (53)
- 2023年4月 (46)
- 2022年12月 (54)
- 2022年11月 (69)
- 2022年10月 (108)
- 2022年9月 (68)
- 2022年8月 (32)
- 2022年7月 (59)
- 2022年6月 (55)
- 2022年5月 (72)
- 2022年4月 (47)
- 2021年12月 (37)
- 2021年11月 (39)
- 2021年10月 (55)
- 2021年9月 (42)
- 2021年8月 (35)
- 2021年7月 (28)
- 2021年6月 (32)
- 2021年5月 (35)
- 2021年4月 (9)
- 2020年12月 (48)
- 2020年11月 (35)
- 2020年10月 (31)
- 2020年9月 (32)
- 2020年8月 (27)
- 2020年7月 (40)
- 2020年6月 (35)
- 2020年5月 (10)
- 2019年12月 (24)
- 2019年11月 (36)
- 2019年10月 (29)
- 2019年9月 (29)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (24)
- 2019年6月 (39)
- 2019年5月 (41)
- 2019年4月 (24)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (21)
- 2018年11月 (21)
- 2018年10月 (21)
- 2018年9月 (22)
- 2018年8月 (19)
- 2018年7月 (22)
- 2018年6月 (23)
- 2018年5月 (39)
- 2018年4月 (35)
- 2018年3月 (1)
- 2017年12月 (19)
- 2017年11月 (21)
- 2017年10月 (22)
- 2017年9月 (26)
- 2017年8月 (24)
- 2017年7月 (31)
- 2017年6月 (32)
- 2017年5月 (30)
- 2017年4月 (14)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (19)
- 2016年11月 (27)
- 2016年10月 (18)
- 2016年9月 (30)
- 2016年8月 (27)
- 2016年7月 (18)
- 2016年6月 (19)
- 2016年5月 (35)
- 2016年4月 (17)
- 2015年12月 (23)
- 2015年11月 (32)
- 2015年10月 (43)
- 2015年9月 (29)