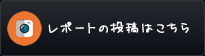担当者より
●446
関西堤防より釣り狂人さん
ジグがアンカーとなり、ラインが張る。
張ったラインというアンテナ、センサー通じて
伝わってくる潮圧とはどこか違う、違和感。
ジグのアンカーポジションが、
魚の接近によって、乱れることによって、
違和感になるのではないかと思っています。
それが、ジグに興味と疑いをもった魚の追尾であることを
知らせてくれます。
「そんなのウソだろ?」、
と思ってたら、一生わからないけど、
「そういうことがあるのかも」、と思って集していたら
間違いなくわかる瞬間がくるはずですし、
一度、二度とそれを経験するうちに
「あぁ、これがそうか」となっていきますから、
ぜひ、そこはここをお読みの皆さんにも味わって欲しい、
ジグの釣りの静なる醍醐味ですね。
わかりやすく言えば
「食い上げ」が、その、最大値のようなもの。
食い上げの「フワッ」という浮遊感
を、10とするなら、
追尾されてる時の違和感は3~8くらいの感じです。
かなりはっきり分かるときもあります。
そのときは、そこから「どう食わすか?」
の醍醐味がめっちゃあり、見切られたときは思わず
「くっそー」と独り言が出て、
早く次の投入をしたくなります。
先日書いた、明石海峡の湾岸青物で使用するラインは
「1.2号」と書きました。
1.5と、2号ではかなり感度は違うし
1.5と、1.2でも違います。
さらに言えば、「強度は持つのか?」
と思われるかも知れません。
その問いには、
「まったく問題ないです」とお答えしてます。
もう25年近く、海峡では、それでやってきています。
湾岸青物の場合、最大サイズでも10キロ前半。
ドラグは直線で2~4キロくらいの方が
ほとんどだと思います。ぜひ一度測ってみてください。
そのドラグで、PE1.2号が切れるでしょうか?
切ろうと思って強く引いてもまず、切れません。
1号でもまず切れません。
ただし1号では、耐久劣化や、根掛かり時の回収、
隣のアングラーとのライン交差時の強度劣化が心配なため、
1.2号が落とし所になっています。
話しを戻しますと、1.2号は、明石海峡では
とてもユーティリティなライン強度だと思います。
海域的に、80センチを超えるようなヒラマサ、
カンパチは滅多に出ず、ブリ中心ですので、可能です。
ハナシを戻せば、それゆえに水中を探知して、
ツバスやハマチ、メジロ、ブリと駆け引きを楽しむ
世界感が成立します。
オフショア有名GT船の船長でも、
GT狙いでドラグ「5キロ」と解説されます。
湾岸ブリ族には、それに見合ったライン設定をすれぱ、
新しい面白さが出てきます。
しかも、ラインクラスは細いとはいえ、
タックルそのものはヒラマサ、キハダ、GTなどの、
6号~10号ロッドを普通に使用できるという
特殊性(ジグウェイトと、飛距離のために)
普段から、離島タックルに
身体を慣らしておくことができることも、
とてもいい釣り場です。
これらは私の子供の頃からのホーム
淡路側、明石側、
海峡最狭部の東西それぞれ
2キロ程度の、狭い範囲でのお話しになります。
潮圧や、追尾
そういうものを感じ取ろうとして釣りをしてるアングラーは、
見ていてわかります。
まず、間違いなく竿は寝ています。
ティップセクションで弾いてジャークいない。
竿のベリーでやわらかに負荷を受け止めることで
ノイズを排除してるんですね。
おそらく釣り狂人さんもそうじゃないかと思います。
なんにせよ、釣れたらそれで楽しいのはそうなんですけど、
あの「感知して釣った」感覚は、
これからも多くのアングラーに知ってほしい
感覚ワールドですね。
潮が速くても、緩くても、変化があっても、
しっかりラインが張ってくれるのが
ジグというルアーの良さだと思います。
これからも、「釣った感」マシマシの、
満足の釣りを展開してください。
レポート有り難うございます。
※自分の通っている波止場では、
持ち物を釣り座に置いての無人場所取りは、マナー違反として、
ローカルマナーで排除されることが御座いますので、
お読みの皆様は留意ください。
また、隣り合ったも何かの縁、
ひと声挨拶してから釣り始めると
1日を心地よく過ごせると思います。
釣り狂人さん、さらに
深めた釣りを展開してください。
レポート有り難う御座います。
●447
●449
新潟より miyaさん
447.449ともいずれもヒラマサを手中にされてますね。
レポートありがとうございます。
新潟というと、ヒラマサの平均サイズ、魚影とも素晴らしい
いくつかの離島を想像します。
サクッと短い時間で状況判断されていたり、
釣行のタイミングの取り方
など、どうやらローカルの方?
でしょうか。
良い釣りをされてます。
また、すべての魚体でフッキング画像
添えてく頂きあり
がとうございます。
あと4ヶ月ほどすれば、
ベイトのトビウオが
見られようになり
大型ヒラマサ一発の
アツい季節がやってきますね。
ST66もパートナーとしていただき
いい釣りができたら、レポートくださいませ。
有り難うございます。
●448
●487
山陰より
@japi3773さん
地磯を歩きに歩いて
の開拓エネルギーが
ムンムン伝わってくるjpiaさんのレポート
画像から、波しぶきがちらまで
飛んできそうな臨場感と笑顔です。
なにげに、ヒラスズキを捉えてるのは
STX45ですね。
45はフォルムが特徴的ですから、
すぐにわかります。
有り難うございます。

No.448では、攻略が困難な「エサについたヒラマサ」を
どうやってバイトに持ち込むかを
書いてくださってます。
私が営業担当していたときから、山陰は
カゴ釣りが盛んなエリアでした。
カゴにオキアミを詰め、磯から投げ、オキアミの帯を
海に作って、マダイやヒラマサをメインターゲットにします。
昔ほどではなくなったと思いますが
いまも、山陰はカゴ釣りが盛ん、
エサ(オキアミ)についた魚は偏食傾向が強く、
ルアーにはなかなか反応してくれませんね。
オキアミのサイズや、色、沈下スタイルに
ルアーを合わせて攻略しようとして、
成功したハナシは一度も聞いたことがありません。
自分も目の前で見たり、経験したりしてきた対処法は、
今回jpiaさんが、示唆してくれている
「ストライクのリアクション」です。
これで、思い出す実例がひとつあります。
上五島の帆揚瀬に、馬場、西浦、吉成の
3人で上礁したときのこと。
午前中、帆揚で釣っていたカゴ釣り師
が帰るとのことで、
私達が、あげてもらうことになりました。
帆揚瀬につくと、そのお二人は、
数もサイズもびっくりするほど
ヒラマサの釣果を上げておられ、
「よく食うよ」と教えてくれました。
ただ、その先の展開が読めてしまうため
3人とも苦笑です。
なにやっても、誰にもヒットしない。
プラグにもジグにもです。
悪い予感的中ですね。
そんななか、唯一のヒラマサ釣果を挙げたのは西浦でした。
ストライク200グラムを、
異様なすっ飛ばし(半ヤケクソくらい激しい)で見せまくり、
そのあとのワンピッチで値千金の1尾をめし捕りました。
これは、jpiaさんのレポート内容と、符合することですね。
オキアミとは、もう全く異次元の反応チャンネルに
マッチさせることで、ヒットを得られたんだと思います。
自分の知る限り、
カゴ釣りが盛んなエリアでは、海が激しくシケて、
リセットされたあと攻めると
明らかに反応が違うと思います。
カゴ釣りの盛んな地域というのは、釣具店や渡船屋さん含めて、
カゴ釣りインフラが完成しているケースがほとんどで、
その一帯すべてが、攻略の難しいことが多いように思います。
また、オキアミを絶えず撒くことで、
魚の偏食を維持する釣り方でもあるため、
ひとりより2人、2人より3人、あるいはそれ以上の
カゴ釣り師さんが入っている釣り場では、
継続的に投入されるオキアミの量も、
絶え間ない継続性も上がりますので、
なかなかルアーでは困難なことも多いように思います。
独立礁での数名での、カゴ釣りの場合は、
一定リズムでカゴを投入し続ける
「観音まわり」という方法が用いられます。
余談ですが、これも
日本の磯釣り文化。
熟練のカゴ釣り師さんの、黙々とした流れるような手返しは、
システムそのものがとてもカッコいいです。
自分もなんどかやってみたことがあり、
魚が食えば、手元から、急にばらばら飛び出ていくラインは
興奮ものです。
ルアーのサイトなんですけど、
なんかカゴ釣り行きたくなってきました。
話しが違う方向っすね(笑)
No.487では
ボディプロテクター4について、
詳しくインプレくださってます、
jpiaさんのように、ハードな地磯釣行を繰り返す方には、
おそらく安心感と、機動軽快性が、
ぴったりハマるのではないかと感じていましたから、
ホッとしています。
今回投ギアのモニターにもエントリーしてくださり、
サポートいただくことになりました。
今後とも、様々な機会が
撃投スタッフから提案されることかと思います。
ぜひお力添えをお願い致します。
※jpiaさんのレポート、皆さんにも読んでもらいたいです。
濃いっす。

- 2010~2015年9月までの過去投稿はこちら (1)
- フィールドテスター (72)
- 担当者2より (51)
- 担当者より (545)
- 撃投サイトへのレポートはこちらから (1)
- 撃投モニター (139)
- 撃投釣果投稿 (2,969)

- 2025年12月 (44)
- 2025年11月 (75)
- 2025年10月 (70)
- 2025年9月 (31)
- 2025年8月 (28)
- 2025年7月 (54)
- 2025年6月 (54)
- 2025年5月 (74)
- 2025年4月 (54)
- 2025年3月 (11)
- 2025年2月 (17)
- 2025年1月 (8)
- 2024年12月 (38)
- 2024年11月 (52)
- 2024年10月 (96)
- 2024年9月 (72)
- 2024年8月 (63)
- 2024年7月 (98)
- 2024年6月 (52)
- 2024年5月 (97)
- 2024年4月 (27)
- 2023年12月 (51)
- 2023年11月 (63)
- 2023年10月 (54)
- 2023年9月 (48)
- 2023年8月 (51)
- 2023年7月 (40)
- 2023年6月 (41)
- 2023年5月 (53)
- 2023年4月 (46)
- 2022年12月 (54)
- 2022年11月 (69)
- 2022年10月 (108)
- 2022年9月 (68)
- 2022年8月 (32)
- 2022年7月 (59)
- 2022年6月 (55)
- 2022年5月 (72)
- 2022年4月 (47)
- 2021年12月 (37)
- 2021年11月 (39)
- 2021年10月 (55)
- 2021年9月 (42)
- 2021年8月 (35)
- 2021年7月 (28)
- 2021年6月 (32)
- 2021年5月 (35)
- 2021年4月 (9)
- 2020年12月 (48)
- 2020年11月 (35)
- 2020年10月 (31)
- 2020年9月 (32)
- 2020年8月 (27)
- 2020年7月 (40)
- 2020年6月 (35)
- 2020年5月 (10)
- 2019年12月 (24)
- 2019年11月 (36)
- 2019年10月 (29)
- 2019年9月 (29)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (24)
- 2019年6月 (39)
- 2019年5月 (41)
- 2019年4月 (24)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (21)
- 2018年11月 (21)
- 2018年10月 (21)
- 2018年9月 (22)
- 2018年8月 (19)
- 2018年7月 (22)
- 2018年6月 (23)
- 2018年5月 (39)
- 2018年4月 (35)
- 2018年3月 (1)
- 2017年12月 (19)
- 2017年11月 (21)
- 2017年10月 (22)
- 2017年9月 (26)
- 2017年8月 (24)
- 2017年7月 (31)
- 2017年6月 (32)
- 2017年5月 (30)
- 2017年4月 (14)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (19)
- 2016年11月 (27)
- 2016年10月 (18)
- 2016年9月 (30)
- 2016年8月 (27)
- 2016年7月 (18)
- 2016年6月 (19)
- 2016年5月 (35)
- 2016年4月 (17)
- 2015年12月 (23)
- 2015年11月 (32)
- 2015年10月 (43)
- 2015年9月 (29)