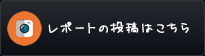【撃投サイト担当者変更と、NEW撃投サイトのお知らせ】
こんにちは、いつも撃投サイトにお立ち寄り
ありがとうございます。
明日から撃投サイトを新担当者の西浦に引き継ぎ、
NEW撃投サイトスタートとなります。
引き続き宜しくお願いします!
私はと言えば、あいも変わらず日々
現役セールスマンとして動きます。
撃投系は、このサイトも含めて、
製品の企画やそれに関わる発売時期、
あるいはSNSでの発信や動画などプロモート全般を
すべてできるだけ引き継ぐことにし、
お声がけ頂いた場合、ショップイベントなどには
時折参加させていただく、、
といった感じのかかわりとなります。
撃投系の業務引き継ぎの代わりに、
以前から予定していた2つのことをはじめます。
ひとつは、20年の長きにわたり連載させていただいた、
SALT WORLD誌の「ハリの話し」を
復活させていただきます。
これは、
SALT WORLD誌のWEB版である、
ANGLERS TIMEさんでの連載とさせていただき、
5月から、スタートさせていただくてもりです。
編集長とは、もうお付き合いも長いので、
今までどおりのノリで
やらせていただけることになっています。
お時間があれば、お立ち寄りくださいませ。
もうひとつは、
これも以前から構想していたことなのですが、
弊社のオリジナルコンテンツとして、
「釣りばりサロン」をゆるっと再スタートします。
コンセプト的には
・エサ、ルアー海、淡水問わず、
釣り全てのレポート歓迎。
・レポートだけでなく、ご質問も歓迎。
これには弊社企画スタッフやテスターからの返信と、
拡がりを見せればいいなぁと思ってます。
一方的発信ではなく、
皆様からのレポートや釣り鈎への疑問を頂くスタイルで、
それに対してスタッフやテスターでお返しするという
2ウェイをめざしたいのです。
自分的には、撃投サイトから学べたことは多いので、
そのノリを釣り全般、河口のハゼも、
ワンドのライギョも、船のマダイも、カワハギも、
ルアーのトラウトもバスも、GTも、、
全部が釣りですし、釣り文化ですから、
それらの共有サイトのハブターミナルになれたらなぁと、
思っています。
そんな共有サイトが育ち、
ソコを見た方がまた何かの形で交流したり、
ひいては私たちの製品理解にもつなげていただけることで、
もちろん弊社利益にも繋がると思ってます。
夏頃にはスタートできるように
社内整備したいと思っています。
なにぶん、営業活動と平行でやりますから
至らぬことも多いでしょうが、
撃投サイトで学んだ「継続は力なり」を信じ、
最強の趣味である「釣り」を、ささやかながら、
しかし、しつこく地道に、
下支えできればと思っております。
「つりばりサロン」は、
コロナの頃の外出禁止の機運の中、
弊社が短期間設けた質問コーナーの名前です。
しっくりきて、いい名前だと思うのでそのまま、
それを用いるつもりです。
そんなこんなです。
明日からいよいよ始まる新撃投サイトを引き続き、
宜しくお願いします。
新担当者の西浦には、
自分のやっていたことを気にすることなく、
すべて自由に思うようにやるのが、
一番自然体で最強のやり方だと思うと伝えて
バトンタッチしています。
宜しくお願いします。
●488 北陸離島より
イエティさん
投げてるタックル一本以外、全部かたずけて
渡船回収ぎりぎりまで投げる、、。
その往生際際の悪さは、自分のような年寄り
でも全くもって、同じです。((笑))
特に自分にだけバイトすらなかった日は、
特別に往生際悪く
まぁ、でもたいていは報われることもなく、
ラスト1投のはずが、なぜか3投して、磯際で
プラグをいつもより数秒ポーズしてみたりして、
やっと、ちいさなため息とともに、
迫りくるエンジン音にあわてつつ、
慌ただしく片づけるといったことを、
この年まで続けてます。
それでも自分は一度も、ラスト●投で
ヒットしたことないんです。
イエティさん、よかったっすね。
これで、ますます「諦めない人」に磨きがかかり、
それは
何よりも強力なメンタルスキルを
得たことになりますから。
あと、シングルのセッティングですが
アユの友釣りでも、3本や4本の
いかりではなく、チラシにする方法がありますが
あれと似たような効果があるかもしれませんね
アユは食わせるわけではなく、魚体に掛けるもので
細かく言えば、事情は違いますけど
水圧負荷に対して、
3本のイカリ型フック→複数本の単バリ
という意味ではよく似ていて、対象物に対して
絡み掛けやすいということになるのかもしれませんね。
イエティさんも、ずいぶんな年数にわたって
撃投サイトの面倒見てくれた方のおひとりですね。
今後も是非、東北や北陸の釣りを深めてください
また、4月1日からの新しい撃投サイトにも是非、
レポートお待ちしております。
引き続きよろしくお願いいたします。
●491 愛媛より
麻衣さん
「これまでの学びをすべて詰め込んだ満足感溢れる釣り」
↑
スゴイお題になってます!
4年ほど前でしたか?すい星のごとく撃投サイトに
現れ、並みいる手練れのアングラーには
手が届かないくらいの釣行頻度と、繰り返される
トライ&エラー、検証。と、それに裏打ちされた釣果。
釣りのことで 「学び」 という表現は
めったに目にしませんけど
麻衣さんならば、しっくりくる。そんな感じがします。
そう感じるのは自分だけでなく、ここに立ち寄る皆さん
認めるところだと思います。
2024【 レポート№491 】
今回、このレポートは凝縮されている。
いままで撃投サイトにいただいた麻衣さんレポートの
どれよりも「エッセンスが凝縮されている」と感じ
ちょっとした神レポートの域だと思います。
これほぢおまで、真面目で謙虚な検証や、
ショア青物の必須要素を、
しかもこの文字数でまとめる釣り人が
いったいどれほどいるのでしょう。
ジグも、プラグも
もっと言えば、餌も、ルアーも
それらすべて、境界などはなくて、
釣りは釣り。
繋がっていますね。
このレポートから伝わりますよ、
麻衣さんはショア青物以外の
どんな釣りをされたとしても、
通常とは比較にならない
ほどの理解と経験を両輪に、
真面目に学んでいくんだろなぁと
そんな風に確信しました。
皆様にも、№491再読をおすすめしたいと思います。
今期もいいシーズンになってきます。
地元愛媛はもちろん、仲間を大事にしながら
さらなる 学び に歩を勧められますよう。
今年のレポートもまた、、楽しみに
お待ちしております。
●493 兵庫県神明間 波止より、中層さん。
中層さんレポート有難うございます。
知らない方のために、「神明間」を補足します。
神戸と明石の区間、明石海峡を含む
東西およそ20キロくらいの海岸線を指します。
大阪湾内ですのでおおむね穏やかな潮流の海ですが、
西は明石海峡のような激流帯も含んで、
この神明間と呼ばれることが多いようです。
中層さんのレポートは、
おそらく明石海峡周辺でしょうか?
「今年は釣れてなかった」と書かれています。
2024年は、どうやらここ数年の中では、
釣れなかった年ようですね。
自分は地元でもあり、おっしゃってることわかります。
その一方で、この10年ほどが
「釣れすぎていた」とも、感じます。
振り返れば、自分が足繁く青物狙いをしはじめたのは
25年ほど前です。
ちなみに、それまでは子供の頃から流れで
カレイやベラ、キスなどの投げ釣りがメインでした。
青物の場合は釣期が7月~9月という3ヶ月。
極めて短い夏の釣りという感じでした。
それもツバス中心で、メジロやブリというのは
まず、釣れないエリアでした。
青物狙いの釣り人も、現在の100分のイチもおらず、
そもそも青物が岸から釣れる
なんていう概念もなかったです。
一部. モノ好きな人だけで投げてました。
めったに釣れなかった。
釣れてるのを見かけるのも、
数回行って一度あるかないか。
ツバスがナブラになったときのみ、、
という感じでしたね。
ヘビージグでボトムから探る釣りは
まだまだ手探りでした。
その状況が変わってきたのは、およそ15年ほど前です。
6月下旬にはツバスのハシリ(1尾目)が
聞こえるようになり、
さらに数年がたち、6月上旬頃にはツバスに混ざって、
メジロやブリも上がりだし、
ショアジギングという言葉もでき、
ムーブメントなっていきました。
そんな時期がしばらく続きました。
さらに時は経ち、
やがて忘れもしないコロナのころとなります。
三密を避けるムーブメントとともに、
釣り人も爆発的に増えました。
「投げるだけで釣れる」なんて、
喧伝するメーカーまで登場したころです。
自分は、あまりに過密する釣り場と、
あまりにも酷すぎるマナーに、ド正直に表現すれば、
辟易としてしまい、釣り場から自然と足が遠のきました。
当時釣り場で顔を合わせていた常連さんも、
ほとんど見かけなくなっていきました。
たまに散歩に行ったとき、
当時の仲間と波止の上で会うとホッとする感じです。
神戸方面のことは詳しくないのですが、
こと、明石はそんなふうな経年変化でした。
釣り人の過密ムードにあわせて、
魚が妙に釣れたことは、果たして、良かったのかどうか?
酷い人も見ました。
撃投ジグで釣ってくれてるのは嬉しいですが、
その方が釣れた魚を足で蹴って
海に放り込むシーンも連続して見ましたし、、。
うんざりしました。
いわゆる釣場作法やマナーの問題は、
その啓蒙が追いつかない凄まじいスピード感で、
マナーを「覚える機会のない」釣り人が増えましたね。
YouTubeなどが一般化した背景もあるのでしょう。
あの明石の激流を前に、
40グラムのジグで釣りが成立するはずがありませんが、
お祭りしたときにほどこうとすると、
PE3号に40グラムなんて、珍しくありませんでした。
語弊を恐れず、気にせず、申し上げますが、
これから平常にもどるのではないでしょうか?
これからが、また本番です。
釣りはもちろん、釣りの世界感を好きで、
大事にする人だけが残ればいいんです。
異論もあるでしょうが私にとってはそれが本音。
釣れない釣りを楽しんめる
平常時に戻っていくのかもせれません。
釣りは、人を選ばない最強の趣味ですから、
多くの人の拠り所になって欲しいものだと、
念じ願ってやみませんが、あまりにもバランスを欠き、
啓蒙が追いつかないスピード感で荒廃するのは、
残念なことです。
私はメーカー社員だからこそ、
「釣りが続くこと」を第一義に思います。
釣業界でもある我々は、
ともすれば売り上げのことを目標だと勘違いする。
傾向もあります。
もちろん数値指標にはなりますが、
実はそれはほんとうの目標とは言えないかもしれません。
あるいは、釣り場釣り人の数=釣り道具やエサの売り上げ
などと短期的に見る。
それもまた少し違うと思いますね。
メーカーも、釣り人も、もしかすると浜の漁師だって
魚がいて、釣り場や漁場などの海が
適正配分の元に保たれて(棲み分けて)、
釣り文化や遊漁文化、漁業が継続すること。
トータルで続いてこそ。だと思うんですよ。
相撲に例えてみます。
土俵がなければ、力士は戦えない。
土俵があってこそ、
力士も行司も、観客も、TV放送も続くんです。
力士や観客が減れば、相撲がなくなりますか?
おそらく、なくなりません。
釣りもそうだと思います。
釣りの環境があればなくなりはしません。
相撲と、釣りを一緒にするなと、
相撲関係者から叱られそうな例えですが、、。
それらは継続していける環境が続いてこそです。
長い目で見ればです。
そこに、釣り人の喜びもついてくる。
釣り文化が続いてこそなんです。
あまりにも、バランスが崩れると、
何処かに歪みがやってくる。
自分は、釣れなければ、
釣れた1尾の喜びが増しますから、
正直、釣れない明石を歓迎します。
そもそも、釣れない釣りなんです。
それを、楽しめるようでいたいと思います。
昔のように。
ここ数年、神明間は少し変でした。
気候の変動もあるのでしょうか?
私にはわかりませんけど、、。
釣れない平常に戻っても全く釣れないわけではない。
言葉は悪いけど釣れることだけを目指す
軽はずみなアングラーは来なくなるでしょう。
歓迎スべきところです。
浜の漁師さんの仕事を邪魔するような駐車する釣り人も
魚を蹴って海にリリース(遺棄)する人も、
ゴミを持ち帰らない人も、
おそらく、そんな属性の方は徐々に減るはずです。
釣れなくなり
人も減る
釣りを大事に楽しめる人だけ、やってくる。
それで落ち着いてくれたらいい。
ガチで私の本音です。
目的は、釣りがなくならず続くことにあるから。
メーカーやブランドは、
モチベーションや志のような芯が失われれば、
淘汰されていく時代が、間違いなくやってきています。
私たちもその、なかにいます。
目指すべきは売り上げではありません。
目標は売り上げなどではなく、「行動」。
その行動の表れが指標としての、「売り上げ」だと
思ってきましたし、いまもそう思っています。
これは、メーカーであれ、釣具店であれ、遊漁船であれ、
同じではないでしょうか?
営業部に所属しているので
そのようなことを、時折り思っていますから、
つい話しが脱線しました、、。
中層さんの今回のレポートでもわかります。
ハリに工夫し、着底後の巻きに思いを巡らせ、
工夫されて楽しまれてます。
なんとか、少ないバイトを捉えようと。
そういう方は、楽しめる。
釣れない釣りに戻る(落ち着く)のでしょう。
自分は大歓迎。
中層さんも大歓迎な人でいてください。
釣り場が、おそらく私とかぶっていますね。
もし見かけたら「中層です」と、
お声がけくださればうれしくおもいす。
撃投サイトにレポートくださった方のサブネームは
忘れっぽい自分の割には、覚えています。
今季も、もうすぐ開幕、
釣れない釣りだからこそ、楽しみましょう。
横道にそれ長くなってしまい、すいません。
明石の激流は、ヒラマサの但馬や隠岐と並び、
撃投ジグのトライ&エラーのすために
なくてはならない場所でした。
引き続きレポートお待ちしております。
※補足として。
明石海峡での釣りに関して、自分が経験してきたことは、
GWにイベントを企画してくださった
「みなと釣具」さんで、お話したいと思います。
とくにリーダーシステムや、潮ごとにかえている竿のこと、
着底後のこと。
独特の激流に対する基本的対処法なども、
経験してこれたことはお話しできます。
神明間では明石海峡は特殊な場所であると思いますので、
これをお読みの皆様で興味ある方がいらっしゃれば、
連休中の貴重な時間ではございますが、
お越しくださいませ。
●496 四国より 八の字さん
釣りバリに関して
非常に嬉しいレポートをくださってます。
素直に、嬉しいですし、
弊社は釣り好きスタッフが多いので、
皆八の字さんのレポートを読めば喜ぶと思います。
ほんと、有難うございます。
さて、ファイアフックもそうですが、
ざっくり言えば、ハリ先には、
ストレートとカーブがありますよね?
ストレートは文字通りまっすぐで、
ジガーライトで言えば早掛、
ジガーミディアムで言えばロックなどが該当します。
一方、カーブはジガーライトで言えば、シワリや、
ジガーライトシリーズではありませんが
ファイアフックがコレにあたり、
ジガーミディアムなら、チェイスということになります。
★ストレートの特徴は
魚に掛かりやすい
★カーブの特徴は
魚に無駄なく貫通し、刺さりやすい
カーブポイントは、魚の口腔部に吸い込まれたときに、
ハリ先が口腔内で立たず(かからず)
口元まで滑り出てくることが多く、
閂を通過する時に初めてハリ先が立ち、
貫通しやすいという
メカニズム的特徴をもっているんです。
また力学的にも貫通力に優れています
(長くなりますので割愛します)
たとえば、イシダイなどは
口の中にほとんど掛かりどころがありませんから、
口元まで引き出されてきて、
閂に掛ける以外選択肢はありません。
ゆえにその全てがカーブです。
昔のイシダイ釣り師の中には、
新品のハリをわざわざハリ先をヤスリで鈍らせて、
「掛かれば絶対カンヌキ」というような
チューンをされている方もおられるほとでした。
なぜ?
カンヌキにかかるという理由はなに?
という、ソコを知っておいていただけると、
フック選択が鮮明にになると思いますので
参考にしていただきたく思います。
ファイアフックが青物の閂を捉えるだけのみならず、
そのゲイブ幅と、ハリ先のカーブの具合が
ジギングの操作に特化したモノであるということも
加味していただければ、
深みも出るのではないかと思います。
釣果レポートよりも、
フックのことを書いてくださったレポートでしたね。
有難うございます。
ハリのことはひとことでお話することは難しいので、
今後もANGLERS TIMEさんや、
つりばりサロンでも、
そういったことを書いていきたいと思っています。
今後とも宜しくお願いします
撃投サイトにも引き続きのレポートをお願いします。
●499 長崎県平戸より
●500 長崎県より
たくぽよさん
長崎県平戸からたくぽよさん
レポートありがとうございます。
今ひとつ魚の追いがよくなかった
感じだったんでしょうか?
ジグのレンジをあまり上下させない状況で
バイトに持ち込むイメージは、
たしか同じく平戸在住で弊社テスターの
岡公一郎さんも話しされてた気がします。
一致するハナシですし、海域的にも近く、
どこかでおそらくそれが最適解なのではないでしょうか?
結果見事にヒラマサからのバイトを引き出されてますので
その水中イメージのナセる結果ですよね!
ところで、ひとつ気になる点といいますが、
添えていただいたヒラマサ画像で、
ストライクに結ばれた連結結束部分に関してです。
拡大したりして見てみたのですが、
ちょっと自分は気になったのは、
スナップで連結されているように見えるからなんです。
拡大してみるとそう見えるんですが、
間違ってたらすいません。
もしスナップなら、あまりお勧めできません。
理由として3つのことを挙げておきます。
①シグ操作時の特殊な衝撃性。
他のルアーと少し異なるのは、ジグの操作では
連結する金属の部分をまるでハンマーで打刻するような
衝撃が加わります。
それがスナップという構造への
耐久疲労に繋がらないかと心配です。
これは決して数値的
検証を伴うものではないですし、
フロロやナイロンリーダーという緩衝装置もありますので、
確かなことではないのですが、
シグがフォール体勢に入ったときに入力すると、
やはりスナップのクランク部分には
負荷がかかりすぎるように思えます。
②絶対強度
スナップの場合は、
同じ線材径でのスプリットリングと比較すると、
その構造的にどうしても引っ張り強度が弱くなります。
また、その開閉のシステム上、
強度的にバランスの取れるスナップは極一部ですし、
もし機械的測定あったとしても、
磯では次の③に挙げるような構造条件が
決定的に影響してきます。
③コンタクトによる開き
スナップは、何かにコンタクトすると
意外とあっさりと開きます。
とりわけメタルジグのように
質量があるのに体積の小さいものが、
その慣性エネルギーで磯や、テトラにコンタクトすると、
ついついスナップのフック部分が外れやすく、
結果として開きやすくなります。
その状態に気づかずに魚とのやりとりしてしまうと
ファイト中ならばあっさり伸びてバレますし、
キャスト前や、ジャーク中に
いつの間にかジグがなくなってしまったりもします。
そのような理由から、
ジグの場合のオススメの連結は、
リーダーをソリッドリングにまず結び、
そこにスプリットリングでシグを取り付ける。
次にアシストフックのリング部分、
スプリットリングに取り付ける。
その連結方法が安全だと思いますので、お試しください。
いまはその方法でセットしてる方が多いと思いますし、
自分もそうしています。
この方法のメリッは、パーツが最小限で抑えられ、
トラブルや強度不安もなく、
ジグの交換も慣れればスナップと大差なく簡単です。
よろしけれはぜひ。
そろそろ、長崎は春マサですね。良い釣りしてください。
またレポートお待ちしております!
有難うございます。
●501山陰より
t-bullさん
t-bullさんレポート有難うございます。
拝読してみると、撃投サイトでも、
文才溢れるレポートを披露してくれるR吉はt-bullさん
の先輩なんすね!
そりゃ、そのメンバーだと
想像しただけでオモシロイ釣行になりそうです。
毎度毎度、釣りは旅を感じるレポート、
有難うです。
今回は定番の王将さんではなく、
珍しくトンカツシーンでしたけど、
いつも釣行後の食事シーンなども
合わせ技のレポートで楽しませてもらえてます。
今後とも、宜しくお願いします。
釣りの方も初日の鳥山わくわく
レガート早巻きの1尾を手にして
2日目の
巨大300ミリプラグ
でのやったったヒラマサずり上げと、
釣りの方も両日ともヒラマサの顔を見れて
バッチリじゃないですか!
なんといってもこの釣りは、ゼロかイチか。
ゼロか、イチ以上か?
そんな釣りですし、両日とも釣果があり、
それもレガート早巻きやら、
巨大プラグの着水音アピール攻撃やら、
王道から少しだけ外れたクワセ方してて、
それはそれは満足度も高かったんじゃないでしょうか?
撃投製品もご愛顧ありがとうございます。
「他のメーカーにないもの」と表現してくれてますが、
リリース当時と違って昨今では、多くのメーカーも
ショア青物カテゴリーを認めてくれるようになり、
一気に類似の製品も増えてますから、
弊社がカテゴリー火付け役になれたことで、
アングラーにとっても
メリットは大きかったのではないかと、
そこもちょっとした満足があります。
カテゴリーとして認識してもらって、
インフラが安定してこそ、
我々の存在や仕事も続きますので。
先週、九州営業の際に
ショップから指摘されたことがあります。
「みんな黒ばっかやなかと??」
なんのことか
わかりますか?
最初、何言われてるのか分からなかったんですが、
突っ込んで聞いてみればつまりこういうことです。
「撃投が、ゲームフローティングベストを
ずっと黒1色で製品展開してきたから、
それがショア青物の
カテゴリーカラーみたいになってしまった。
そうなるとカラー展開が黒だけになって、
色の選択肢が狭い。他の色があれば、もっと売れるのに」
というわけです。
その方はもうベテランスタッフですから、
業界最古のロックショアベスト。
ゲームフローティングベストのことを覚えています。
ショップスタッフならではの視点で、
そういう見方もあるんだなぁと、これには苦笑。
大手メーカーほど、販売力のない
つりばり専門メーカーが、ライジャケや
竿ケース企画するとなると、
そんなに数作る力がないから、
素材カラーを何色も展開できなくて、
それで、ほとんど黒でやってきたのが内情です。
いまとなっては、たしかに。
ロックショア、ほとんどのメーカーさんのものが黒ですね。
ご指摘で初めて気づくことがあります。
さて、t-bullさん、
自分は撃投についてはある程度、
当初の目標だった「磯釣り文化の末席に」まで、
これだと思ってるんです、
今後は仕事を後輩にお願いし、
サポートくらいの感じでやりますが、
手を抜くことはないと思います。
引き続き宜しくお願いしたいですし、
レポートお待ちしてます!
有難うございます。
●502
兵庫より、ぶりぶり大根さん
ぶりぶり大根さん
レポート有難うございます。
そうですね。激戦区で横並び、
しかも隣の人との間隔があまり取れない釣り場、
しかも潮の流れがあるなかでプラグでとなると、
マクロのタイミングとしては、
潮の緩んでるときを狙うのはもちろんだし、
ミクロ的には、両隣の方のキャストタイミングと着水点、
流れ方を、毎投よく見ながらじゃないと釣り辛いですね。
そこをうまくツイての1尾、ナイスメジロっす!
文中にてご質問の、
「フィードポッパーに、湾岸でST66でよいのか?」
について。
メーカー様推奨なので、それが一番だと思います。
もしアレンジするのなら2つの視点があると思います。
①ルアーの浮き姿勢やアクションへの影響
②魚へのフッキング
そのふたつです。
①についてはメーカーさんの推奨ですから、
そのまま66がベストだと思います。
②については、大阪兵庫湾岸なら
ヒラマサやカンパチは少なくブリがメイン。
また15キロを超える魚はめったに出ないでしょうし、
自分の知ってる範囲でも14キロが上限です。
そうなると、強度的には
パークラス5のSTX58を、ご利用いただければ、
フッキング、そして貫通力、
そのどちらも66よりも優れると思います。
この場合、66と同じ浮き姿勢や
アクションを再現するために、重量を揃える
(つまり66よりワンサイズ大きいフックを選ぶ)
ことが、肝要だと思います。
ハリ先が鋭利になるぶん、
バイトがあればシャープに拾うと思いますので、
よかったらお試しください。
ぶりぶり大根さんも、
撃投サイトを楽しんでくださってました。
ありがたいコメントを文中でいただき、感謝です。
ぶりぶり大根さんが大事にしている、投げ続けること。
それは、ほんとうにこの釣りでは大事なことですし、
自分もそうでいたいと思っています。
このぶりぶり大根さんへのコメントをもって、
自分の担当者よりは、終了です。
皆様のおかげで、楽しい撃投の仕事に没頭できてきました。
ほんとうに、ユーザーさんが撃投を支え、
育ててくださったおかげですよ。
その一念で、続けてこれました。
今後とも、皆様も良い釣りを。
引き続きニュー撃投サイトを宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。
吉成秀人


- 2010~2015年9月までの過去投稿はこちら (1)
- フィールドテスター (72)
- 担当者2より (51)
- 担当者より (545)
- 撃投サイトへのレポートはこちらから (1)
- 撃投モニター (138)
- 撃投釣果投稿 (2,968)

- 2025年12月 (43)
- 2025年11月 (75)
- 2025年10月 (70)
- 2025年9月 (31)
- 2025年8月 (28)
- 2025年7月 (54)
- 2025年6月 (54)
- 2025年5月 (74)
- 2025年4月 (54)
- 2025年3月 (11)
- 2025年2月 (17)
- 2025年1月 (8)
- 2024年12月 (38)
- 2024年11月 (52)
- 2024年10月 (96)
- 2024年9月 (72)
- 2024年8月 (63)
- 2024年7月 (98)
- 2024年6月 (52)
- 2024年5月 (97)
- 2024年4月 (27)
- 2023年12月 (51)
- 2023年11月 (63)
- 2023年10月 (54)
- 2023年9月 (48)
- 2023年8月 (51)
- 2023年7月 (40)
- 2023年6月 (41)
- 2023年5月 (53)
- 2023年4月 (46)
- 2022年12月 (54)
- 2022年11月 (69)
- 2022年10月 (108)
- 2022年9月 (68)
- 2022年8月 (32)
- 2022年7月 (59)
- 2022年6月 (55)
- 2022年5月 (72)
- 2022年4月 (47)
- 2021年12月 (37)
- 2021年11月 (39)
- 2021年10月 (55)
- 2021年9月 (42)
- 2021年8月 (35)
- 2021年7月 (28)
- 2021年6月 (32)
- 2021年5月 (35)
- 2021年4月 (9)
- 2020年12月 (48)
- 2020年11月 (35)
- 2020年10月 (31)
- 2020年9月 (32)
- 2020年8月 (27)
- 2020年7月 (40)
- 2020年6月 (35)
- 2020年5月 (10)
- 2019年12月 (24)
- 2019年11月 (36)
- 2019年10月 (29)
- 2019年9月 (29)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (24)
- 2019年6月 (39)
- 2019年5月 (41)
- 2019年4月 (24)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (21)
- 2018年11月 (21)
- 2018年10月 (21)
- 2018年9月 (22)
- 2018年8月 (19)
- 2018年7月 (22)
- 2018年6月 (23)
- 2018年5月 (39)
- 2018年4月 (35)
- 2018年3月 (1)
- 2017年12月 (19)
- 2017年11月 (21)
- 2017年10月 (22)
- 2017年9月 (26)
- 2017年8月 (24)
- 2017年7月 (31)
- 2017年6月 (32)
- 2017年5月 (30)
- 2017年4月 (14)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (19)
- 2016年11月 (27)
- 2016年10月 (18)
- 2016年9月 (30)
- 2016年8月 (27)
- 2016年7月 (18)
- 2016年6月 (19)
- 2016年5月 (35)
- 2016年4月 (17)
- 2015年12月 (23)
- 2015年11月 (32)
- 2015年10月 (43)
- 2015年9月 (29)